中学受験理科講座
中学受験理科 一問一答プリント集はこちらをクリック
中学受験理科 オンラインテストはこちらをクリック

Haru_You
はじめまして、ここは中学受験理科講座のページです。
算数文章題講座同様、先生役を務めます筆者のHaru_Youです。
算数文章題講座同様、先生役を務めます筆者のHaru_Youです。
ここでは、中学受験で使う理科の各単元ごとの解説動画と、その演習としての一問一答演習プリントを公開しています。

はるか

Haru_You
まだ作成途上なのでコンテンツが不十分ですが・・・
中学受験理科 生物
植物のつくりとはたらき(2)〜根・茎・葉〜

Haru_You
この単元では植物のからだのつくり、根・茎・葉について、植物の分類と合わせて詳しく説明していくよ。
また覚えることが多そうだね。
植物の種類ごとに覚えないといけないんでしょ?
植物の種類ごとに覚えないといけないんでしょ?

はるか

Haru_You
種類ごと、といっても大きく分けて双子葉類と単子葉類の2種類に分けるだけなんだ。
異なる点をきちんと覚えれば大丈夫。
異なる点をきちんと覚えれば大丈夫。
動物とヒトのからだ(1)~消化と吸収~

Haru_You
ここではからだの仕組みのうち、消化と吸収に関する内容を取り扱うよ。
具体的にはどんな内容なの?

はるか

Haru_You
栄養素の名前と、栄養素ごとにどこで消化されるか内臓の名前、そして消化をおこなう消化酵素なんかを覚えてく必要があるかな。
逆に言えば、覚えるだけでいい単元なので、比較的とりくみやすい単元だよ。
逆に言えば、覚えるだけでいい単元なので、比較的とりくみやすい単元だよ。
動物とヒトのからだ(2)~呼吸と循環~

Haru_You
こっちの単元では呼吸と循環、すなわち肺と心臓、それから腎臓のはたらきについて説明するよ。
ここも覚えるだけで大丈夫?

はるか

Haru_You
そうだね、たまに血中酸素や循環血液量の計算が出るけど、ただの割合計算なんだよね。
そういう問題が出てきたときに悩まないよう、きちんと言葉の意味を理解していれば大丈夫だね。
そういう問題が出てきたときに悩まないよう、きちんと言葉の意味を理解していれば大丈夫だね。
生物どうしのつながり
生物どうしのつながりって、食物連鎖ってこと?

はるか

Haru_You
食物連鎖についても取り上げるけど、メインは植物群落の話かなあ。
あまりテストで見ない内容だね。

はるか

Haru_You
環境問題とかと組み合わせた形で出題されるから、今後出題の増える単元だとは思うよ。
あまり覚え込む必要はないけど、よく読んでイメージできるようにしておいてね。
あまり覚え込む必要はないけど、よく読んでイメージできるようにしておいてね。
中学受験理科 地学
星の動き
星座はたくさんあるし、季節ごとにでてくるから覚えるの大変なんだよね。

はるか

Haru_You
たくさん、ていうけど、名前の出てくる星座は15個くらいだから、そこさえ覚えちゃえばすごい簡単になる単元だよ。
何月何時にどこに見えるとかも難しくない?

はるか

Haru_You
あれも、1ヶ月・2時間で30度動くって決まり覚えるだけだからね。
星の動きは勉強しやすい単元だから、早めに完璧にするといいよ。
覚えちゃえば、夜空で星を見るのが楽しくなるしね。
星の動きは勉強しやすい単元だから、早めに完璧にするといいよ。
覚えちゃえば、夜空で星を見るのが楽しくなるしね。
月の満ち欠け
月の満ち欠けって、いつどっちに何の月が見えるとかややこしいよね。

はるか

Haru_You
「いつ」と「どっち」をバラバラで覚えるからややこしいんだよ。
月の見え方には法則があるからそのルールをしっかり覚えればいいんだ。
月の見え方には法則があるからそのルールをしっかり覚えればいいんだ。
じゃあ、ルールを読みながら毎日月を見てれば、覚えられるかな?

はるか

Haru_You
そうだね、気象や天体は実際に観測することが一番勉強になるよ。
地球と太陽(1)

Haru_You
ここでは地球上の緯度経度、太陽の日周運動と南中について扱うよ。
地学範囲っていうと知識問題が多いイメージだけど、ここは計算問題があるんだよね。

はるか

Haru_You
時差や南中時刻の計算だね。
ルールさえわかれば、それほど難しい計算はしないから大丈夫だよ。
ルールさえわかれば、それほど難しい計算はしないから大丈夫だよ。
地球と太陽(2)

Haru_You
こっちでは太陽の年周運動と、各地での季節ごとの太陽の動きについて説明するよ。
透明半球とか日影曲線とか、図になってるものが多く出てくるよね。

はるか

Haru_You
うん、文章と図の両方で理解しておくことがこの単元では大切になるよ。
大地の変化(1)

Haru_You
ここは地層とたい積岩の内容なんだけど、塾教材では4年生配当になってる流水のはたらきも合わせてここで解説しちゃうよ。
岩石の名前とか、覚えることばっかなイメージあるけど。

はるか

Haru_You
いや、そんなたくさんあるわけじゃないから、面倒くさがらずに覚えてみな。
すぐにできるようになるから。
すぐにできるようになるから。
大地の変化(2)

Haru_You
こっちは火山と地震について。
前回と同様、あれこれ専門用語が飛び交うけど、それを1つ1つ覚えていくこと
前回と同様、あれこれ専門用語が飛び交うけど、それを1つ1つ覚えていくこと
でも、地震のこととか知っておいたほうがいいよね。
大きい地震が今後も起きる可能性はあるんだし。
大きい地震が今後も起きる可能性はあるんだし。

はるか

Haru_You
この単元もそうだけど、理科の知識は実際の生活の中で使うことで覚えやすくなるからね。
この現象が、教科書に書いてあったことだなあって思いながら、火山や地震のニュースを見ればすぐに覚えられるよ。
この現象が、教科書に書いてあったことだなあって思いながら、火山や地震のニュースを見ればすぐに覚えられるよ。
地球と宇宙

Haru_You
ここは地学系単元の総復習的な意味合いもありつつ、ここまでとりあげていない地質時代や惑星の見え方なんかも扱っていくよ。
そういえば月と星座はやったけど、金星はやってなかったっけ。

はるか

Haru_You
内容があれこれ分散してるけど1つ1つ覚えておいてくれ。
覚えちゃえばできる単元なんだから。
覚えちゃえばできる単元なんだから。
中学受験理科 物理
光の性質
光って、レンズとか屈折とかやるやつだよね。
あれ、すごい苦手なイメージがあるんだよなあ。
あれ、すごい苦手なイメージがあるんだよなあ。

はるか

Haru_You
この単元は、物理の他の単元と絡まずに1回完結なので、1度やったきりあまり見かけなくなるから定着しづらいんだよね。
予習シリーズだと5年上の夏休み前に1度やるっきりだからね。
レンズや屈折部分の内容自体は単純なルールなので、きちんと覚えれば大丈夫だよ。
予習シリーズだと5年上の夏休み前に1度やるっきりだからね。
レンズや屈折部分の内容自体は単純なルールなので、きちんと覚えれば大丈夫だよ。
音の性質
光に続いて音か。
音の問題ってあまりテストで見た記憶がないんだけど・・・
音の問題ってあまりテストで見た記憶がないんだけど・・・

はるか

Haru_You
うん、実際この単元が一番内容薄いかも。
覚えることも多くないし、計算問題もモノコードと反射の音速くらいだからね。
5年生の前半で勉強しちゃうと後はでてこないから、光と同じように復習しないから覚えていないだけ、ってことが多い単元だよ。
覚えることも多くないし、計算問題もモノコードと反射の音速くらいだからね。
5年生の前半で勉強しちゃうと後はでてこないから、光と同じように復習しないから覚えていないだけ、ってことが多い単元だよ。
電流と抵抗

Haru_You
ここでは、豆電球と乾電池のつなぎ方による、明るさと電流量の変化について説明するよ。
直列つなぎと並列つなぎってやつだよね。
単純な回路ならわかるんだけど、つなぎ方が複雑になるとわかんないんだよなあ。
単純な回路ならわかるんだけど、つなぎ方が複雑になるとわかんないんだよなあ。

はるか

Haru_You
最近は複雑な回路図と抵抗計算の問題はあまり入試で人気がないんだよね、結局中学に入ってオームの法則で覚え直す羽目になるから。
なので基本的なパターンだけしっかり押さえれば大丈夫だよ。
なので基本的なパターンだけしっかり押さえれば大丈夫だよ。
電流と磁界

Haru_You
前講に続いての電流がテーマで、ここでは電流によって生じる磁界と、コイルや電磁石のしくみを説明するよ。
導線に電流を流すと、方位磁針がどっちにふれますかってやつか。
あとはコイルのどっちがN極ですか、とか。
図によって異なるからややこしいんだよね。
あとはコイルのどっちがN極ですか、とか。
図によって異なるからややこしいんだよね。

はるか

Haru_You
ややこしそうに見えて、動き方は4パターンしか存在しないからルールさえ覚えれば楽勝なんだよ、この単元は。
右手を使うだけで全部求められるから、ルールをしっかり覚えよう。
右手を使うだけで全部求められるから、ルールをしっかり覚えよう。
電流と発熱

Haru_You
さらに電流テーマがもう1つ。
ここでは電熱線の発熱のしかたと、つなぎかたによる違いについて説明するよ。
ここでは電熱線の発熱のしかたと、つなぎかたによる違いについて説明するよ。
電熱線は全部比例と反比例だから簡単だよね。

はるか

Haru_You
うん、確かに簡単。
実はこっちを理解してからもう一度電流と抵抗に戻ると、より理解しやすくなるんだよね。
実はこっちを理解してからもう一度電流と抵抗に戻ると、より理解しやすくなるんだよね。
ばねの性質

Haru_You
ここからは力学系単元が続くよ。まずはばねの性質。
ばねは計算だけど、のび方が比例だからそんなに難しくないよね。

はるか

Haru_You
難しくしようと思えばいくらでも難しくできるけど、今時そんな問題テストに出ないからね。
基本パターンをしっかり理解できればここは大丈夫。
基本パターンをしっかり理解できればここは大丈夫。
ものの運動と振り子

Haru_You
力学系単元の2つめは、ものの運動と振り子。
ここは1つだけルール覚えたら、あとは「当たり前」の感覚で考えればわかる単元だね。
ここは1つだけルール覚えたら、あとは「当たり前」の感覚で考えればわかる単元だね。
当たり前て、例えばどういうこと?

はるか

Haru_You
重いおもりや速いおもりをぶつけたら衝撃が大きくなるってこと、それって当たり前だろ。
物理ってのは、この世界で起こる現象を言葉にしてルール化したものなんだから、日常生活で当たり前に感じていることがそのまま出てくるんだよ。
物理ってのは、この世界で起こる現象を言葉にしてルール化したものなんだから、日常生活で当たり前に感じていることがそのまま出てくるんだよ。
てこの性質

Haru_You
続いては、てこの性質。
てこというか、ほとんどがてんびん計算なんだけどね。
てこというか、ほとんどがてんびん計算なんだけどね。
てんびんの計算は複雑で難しいなあ。

はるか

Haru_You
計算で使うルールは左右のモーメントのつりあいと上下の力のつりあいだから、きちんと基本を理解して。
力学が入試で出る場合、いちばんよく出るのがこの単元だからね。
力学が入試で出る場合、いちばんよく出るのがこの単元だからね。
滑車と輪軸

Haru_You
力学単元がまだまだ続いて、今度は滑車と輪軸。
まあ、てこを理解していればそんなに難しくない単元だね。
まあ、てこを理解していればそんなに難しくない単元だね。
輪軸って結局のところ、てこと同じルールだもんね。

はるか

Haru_You
とにかく物理単元はルールを覚えるのが肝心だからね。
ルール通りに計算すれば、必ず正解が出せるから、練習すれば得意単元にできるはずだよ。
ルール通りに計算すれば、必ず正解が出せるから、練習すれば得意単元にできるはずだよ。
圧力と浮力

Haru_You
ようやく力学単元の最後、圧力と浮力だね。
ここはあまり複雑な問題を作れないし、他の単元との絡みも薄いから先にやっちゃってもいいんだけどね。
ここはあまり複雑な問題を作れないし、他の単元との絡みも薄いから先にやっちゃってもいいんだけどね。
浮力が水中の体積で計算できることと、ピストンが底面積に比例して力が必要なことさえ覚えていれば大丈夫かな。

はるか

Haru_You
まあ、よく出るのはその2つだね。
だけど物理単元は、最初の1問目で求めた数字を次の問題でも使うときに、1問間違えると全部間違える危険があるから、できるだけ完璧にしておくことね。
だけど物理単元は、最初の1問目で求めた数字を次の問題でも使うときに、1問間違えると全部間違える危険があるから、できるだけ完璧にしておくことね。
中学受験理科 化学
気体の性質

Haru_You
ここでは酸素と二酸化炭素を中心に、気体の性質とその発生法、そして発生量の計算について説明するよ。
薬品の名前も多いし、何より計算が大変だよね・・・

はるか

Haru_You
計算といっても、ほとんどは比例計算だけだから、たくさん解いて慣れれば簡単だよ。
水溶液の濃さと溶解度
この単元もまた、計算だらけだよねえ・・・

はるか

Haru_You
うん、しかも他の化学単元と違って比例計算じゃないから大変かもね。
濃さの計算は算数でもやるから、そちらも見ておいてね。
濃さの計算は算数でもやるから、そちらも見ておいてね。
この単元は濃さの計算以外にはなにかあるの?
ないなら算数でやればいいかな、と思うんだけど。
ないなら算数でやればいいかな、と思うんだけど。

はるか

Haru_You
溶解度から結晶の析出量を求める問題が、この単元でやる内容だね。
実際のところ濃度の計算より、結晶量の計算のほうがテストによく出るからね。
実際のところ濃度の計算より、結晶量の計算のほうがテストによく出るからね。
水溶液の性質(1)
水溶液の性質っていうけど、水溶液なんてすごいたくさん種類あるんじゃないの?

はるか

Haru_You
そりゃ何千何万種類とあるけどね、中学受験の内容で、しかもその性質や識別が出る水溶液はいいとこ11種類くらいなんだよ。
ここでは水溶液の性質による識別方法と中和について説明するよ。
ここでは水溶液の性質による識別方法と中和について説明するよ。
中和って、また計算問題出てくるよね。

はるか

Haru_You
計算問題だけど、ほとんど比例計算だけで処理できるから簡単だよ。
計算に入る前にまずしっかり性質を覚える方が化学では大事だから、計算単元だって勘違いしないようにね。
計算に入る前にまずしっかり性質を覚える方が化学では大事だから、計算単元だって勘違いしないようにね。
水溶液の性質(2)
こっちは何を説明するの?

はるか

Haru_You
水溶液に金属を溶かして気体が発生するときの反応について、だね。塩酸と水酸化ナトリウム水溶液が主役になるので、前の回でよく理解してからここに入ってね。
気体の発生も別の回で説明してるよね。

はるか

Haru_You
それだけテストで良く出るところなんだよ、ここは。
基本知識をしっかり覚えて、比例計算をマスターすれば得点源になりやすいから頑張って。
基本知識をしっかり覚えて、比例計算をマスターすれば得点源になりやすいから頑張って。

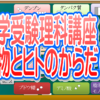
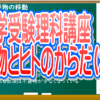
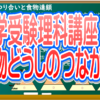
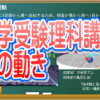
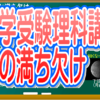
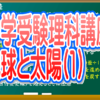


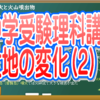
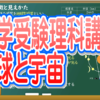
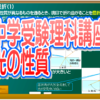
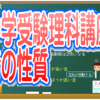
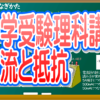
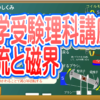


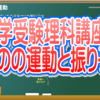

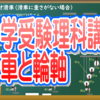
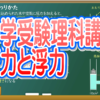
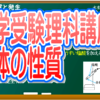


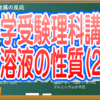
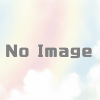


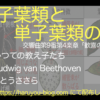
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません